第1章:レジ係という仕事の進化と現状
1879年に登場したリティ・キャッシュレジスターから始まり、1974年には世界初のバーコード読み取りが実用化されました。さらに1990年代のスキャナー式POSを経て、2020年代にはセルフレジやモバイル決済が主流となりつつあります。まずは、このおよそ150年に及ぶ変遷を振り返り、レジ係の役割がどのように変化してきたのかを確認しましょう。
日本リテール協会の調査によると、2024年時点で18〜59歳の91%がセルフレジを利用した経験があると回答しています。また、米国でも86%が同様の経験を持ち、セルフレジは国や文化を問わず急速に浸透しています。POSシステムの高機能化に伴い、「ピッ、ピッ」とバーコードを読むだけの単純作業は縮小し、接客や売場改善、顧客体験設計といった高付加価値領域へとレジ係の仕事内容が拡張されつつあります。
まとめ:レジ係は「決済オペレーター」から「顧客体験マネージャー」へと進化しています。つまり、機械化=雇用減ではなく、業務再編が進行していると言えるでしょう。
第2章:AIによる自動化の波とセルフレジの裏側
無人決済店舗が注目を集める背景には、顧客体験向上と人手不足という二つの課題を同時に解決したいという小売各社の思惑があります。
たとえば、AmazonのJust Walk Outテクノロジーは、天井カメラ・重量センサー・RFIDタグを組み合わせて顧客の動線と商品選択をリアルタイム追跡し、レジでの待ち時間を完全に排除しています。2024年の導入店舗数は前年比30%増を記録しました。一方、台湾企業Viscoveryのカメラレジは1秒未満で複数商品を識別し、バーコードのない総菜やパンも正確に読み取ります。国内ではファミリーマートがTouch To Go方式を採用し、2025年度末までに1,000店舗への導入を目指しています。
まとめ:セルフレジに組み込まれたAIは、単なるレジ機械の置き換えではなく、需要予測や発注自動化などバックエンド業務にも波及する「店舗オペレーション全体の司令塔」となっています。
第3章:消えるだけではない—「監視者」としてのレジ係の新しい立場
AIが万能に見える一方で、例外処理やセキュリティ分野では依然として人間の介在が欠かせません。
英国の大手スーパーマーケットチェーンでは、万引きや支払エラーによるShrinkage(小売損失)が年間売上の2〜3%に達すると報告されています。AIカメラが不審行動を検知できても、年齢確認や酒類販売制限、障がい者サポートなど、最終判断には人の目が必要です。米国では、複数店舗を遠隔支援するRemote Associateという職種が誕生し、ビデオ通話で顧客対応を行う体制が整いつつあります。従来1店舗6〜8名だった配置が3〜4名となる一方、彼らの役割は「決済」ではなく「監視・例外対応」へと高度化しています。
まとめ:レジ係は「消える」どころか、AIを補完するStore Guardianとして、例外対応とセキュリティの要となる新たな専門職へ移行しています。
第4章:無人店舗の心理的バリアとユーザー体験の課題
技術が整っても、利用者の心理が追いつかなければ真の普及は望めません。
オーストラリアの調査では34%が「セルフレジは面倒」と回答し、英国でも48%が有人レジを選択すると言われています。高齢者からは「タッチパネルの文字が小さい」、子育て世帯からは「商品登録ミスの訂正が面倒」といった声が寄せられています。また、無人店舗は「見られていない不安」から万引きを誘発するリスクが指摘されており、その結果、AIカメラと警備スタッフの配置を強化せざるを得ないというジレンマが生じています。国内では「セルフレジ案内係」を常駐させ、操作サポートと声かけで心理的バリアを軽減する取り組みが広がっています。
まとめ:無人化を成功させる鍵は「効率」と「安心感」の両立です。人的インターフェースの再設計がユーザー体験を左右します。
第5章:未来のレジ体験はどこへ向かうのか?
セルフ化の次は「レジ消失」— 決済が空気のように溶け込む時代が到来しようとしています。
AI搭載スマートカートは、商品を投入すると同時に重量を測定し、カゴをレジに置く手間すら省きます。市場調査会社GlobalDataによれば、アジア太平洋地域のセルフレジ関連市場はCAGR 15.8%で成長し、2028年には300億米ドル規模に達する見込みです。しかし、2025年にAmazonがJust Walk Outを補完する有人サポートを再強化したように、完全自動化だけが未来ではありません。実際、AI決済を裏方に配置しつつ、スタッフが体験型サービスを提供するハイブリッド型店舗では、客単価が1.3倍に向上した事例も報告されています。
まとめ:未来のレジは「ない」のではなく「見えない」だけ。AIが裏方に回り、人は“買い物の楽しさ”を演出するステージマネージャーへと進化していくでしょう。


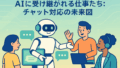
コメント